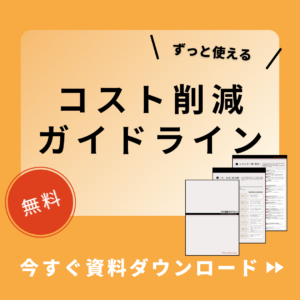近年、企業の価値を見極める指標としてPBRに注目が集まっています。PBRとは、企業の株価がその企業の資産価値に対してどの程度評価されているかを測るために用いられる指標です。一般的に、PBRは高いほうがよいとされますが、業種・業種によって平均値が異なるほか、一時的な影響から数値が低下しているといったケースもあります。そのためPBRを用いる際は、その性質や留意点を知って必要があります。
この記事では、PBRの目安と「1倍割れ」の意味や課題、PBR改善に向けた経営戦略とコスト最適化について解説します。また、PBRを活用する際の留意点も解説していますので、参考にしてください。
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。
PBRとは?

PBR(Price Book-value Ratio)とは、株価と企業の帳簿価値(純資産)との比率を示す指標のことです。企業の株価がその企業の資産価値に対してどの程度評価されているかを測るために用いられます。
PBRは、企業の資産に対して投資家がどれだけの価値を支払っているかを示す指標でもあるため、外部からの企業評価や、投資判断において重要な役割を果たします。
PBRの計算式
PBRは次の計算式で求められます。
PBR=株価÷1株当たりの純資産
1株当たりの純資産とは、企業の総資産から負債を引いた純資産を発行済株式数で割ったものです。
PER(株価収益率)との違い
PBRと混同されやすい指標にPERがあります。
PER(Price Earnings Ratio)は株価収益率とも呼ばれる指標で、株価と企業の利益との比率を示す指標です。
PERが高い場合、市場が企業の成長性を高く評価していることを示し、将来の利益成長が期待されている場合が多いです。PERが低い場合、市場が企業の成長性に対して懐疑的であることを示し、業績の悪化や競争力の低下が懸念されることが多いです。
PERは次の計算式で求められます。
PBR=株価÷1株当たりの利益
PBRとPERはいずれも株価をもとにした指標ですが、PBRが企業の資産価値に基づいて株価を判断するのに対し、PERは企業の収益性に基づいて判断します。PBRは資産の評価を、PERは利益の評価を重視した指標といえます。
このため、PBRは資産の健全性や評価を重視して企業を見極める際に用いられ、PERは企業の将来の利益成長を重視して企業を見極める際に用いられるといえます。
いずれかの指標のみで企業を判断するよりも、これらを組み合わせて総合的に企業の価値を判断すべきですが、業界・業種、市場環境などに合わせて適切な指標を用いることが、効果的な判断につながるとされています。

PBRの目安と「1倍割れ」の意味

一般的に、PBRがどの程度であれば評価を得ているといえるのか、「1倍割れ」と呼ばれる状態はどういったものなのか解説していきます。
PBRが1倍以上であれば、一般的に市場はその企業の資産価値を評価していると考えられます。一方、PBRが1倍未満の場合、市場はその企業の資産価値を十分に評価していない可能性があります。
この「PBRが1倍未満の場合」は「1倍割れ」とも呼ばれ、市場がその企業の資産価値を低く見積もっている可能性を示します。これには、企業の業績や将来の成長性に対する懸念が反映されているケースが多いです。
ただし、PBRが低いからといって必ずしも株価が割安状態に陥っているとは限りません。
例えば、業績が悪化している企業や、資産の評価に問題がある企業は、PBRが低くなることがあります。一時的に上記のような状態にあるためにPBRが低くなることもあるため、PBRだけで投資判断を行うのは確実といえません。

PBRが低い企業に共通する課題とは?

PBRが低い理由はさまざまですが、PBRが低い企業に共通する課題として次のような点が挙げられます。
- 収益性の低さ、資産の有効活用不足
PBRが低い企業は収益性が低いことが多く、資産を十分に活用できていない場合があります。これにより、企業の価値が市場で正当に評価されていないことがあります。
- 経営効率の悪さ、成長戦略の不明確さ
経営効率が悪い企業ではコストがかさみ、利益が圧迫されるケースが多く、PBRが低くなる傾向があります。また、成長戦略が不明確な企業は、将来の成長が見込めず、投資家からの評価が低くなることがあります。
- コーポレートガバナンスの弱さ
コーポレートガバナンスが弱い企業は、経営の透明性が欠如していることから投資家からの信頼を得られず、PBRが低くなることがあります。これにより、企業の資産価値が適切に評価されない可能性があります。
この他の要因がPBRの低さにつながっている可能性もありますが、まずは上記の点を確認してみましょう。

PBR改善に向けた経営戦略とコスト最適化

PBRを改善するためには、単に株価を上げるだけでなく、企業の実力を高める必要があります。その鍵となるのが、収益力の強化とコスト構造の最適化です。
収益力の強化とコスト構造の最適化の具体的なアプローチとして、次の4つをご紹介します。
- 間接費や固定費の見直しによる利益率の改善
- サプライチェーンの統廃合による効率化
- 非効率な業務プロセスの再設計(BPR)
- 使われていない資産・施設の売却や活用
これらの施策を通じて、企業の収益性と資産の有効性を高めることで、結果としてPBRの改善につながります。それぞれについて詳しく解説していきます。
間接費や固定費の見直しによる利益率の改善
間接費や固定費を見直すことで、利益率の改善につながり、結果としてPBRを向上させることができます。
サプライチェーンの統廃合による効率化
サプライチェーンの統廃合を行うことで、コスト削減や効率的な運営を実現することが可能になります。結果として、PBRの数値も高まる効果が期待できます。
非効率な業務プロセスの再設計(BPR)
業務プロセスを再設計することで、非効率な部分を排除し、全体の効率を向上させることができます。
こういった取り組みはBPR(Business Process Re-engineering)と呼ばれ、近年、企業が抜本的な業務改革を行う手法として注目されています。
使われていない資産・施設の売却や活用
使われていない資産や施設を売却、または最適に活用することで、資産の有効性を高めることができます。企業の資産価値が高まり、PBRの改善につなげることができます。

PBRを活用する際の留意点

PBRという指標を活用して企業をみる際、留意すべきポイントも存在します。ここでは、主なポイント3つについて解説します。
1.業種による違い
PBRの平均値や優良値は業種によって大きく異なります。そのため、企業のPBRを見極める際は同じ業種内の企業と比較するといった工夫が必要となります。
例えば、2025年4月時点では、製造業のPBRは1.1倍、銀行業では0.4倍となっています。
このように、業界・業種によって水準が異なるため、業種を考慮した分析が必要です。
参考:https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/misc/04.html
2.含み資産の未反映
PBRは企業の帳簿上の資産価値に基づいているため、土地や知的財産などの簿外資産が反映されていないことがあります。これにより、実際の企業価値が過小評価される可能性があります。
3.一時的要因の影響
先にも触れましたが、株価が下落するなど、一時的な要因でPBRが1倍を下回ることがあります。PBRが低い状態にある場合、一時的な要因がないか考慮することが重要です。

まとめ
本記事で解説したPBRとは、企業の株価がその企業の資産価値に対してどの程度評価されているかを測るために用いられる指標です。一般的にPBRは高いほうがよいとされており、PBRが1倍以上であれば市場が企業の資産価値を評価しているとされ、1倍未満は「1倍割れ」と呼ばれる資産価値が低く見積もられている状態といえます。
ただし、PBRは業種・業種によって平均値が異なるほか、一時的な影響から数値が低下している可能性、含み資産の未反映である可能性があるため、PBRを活用する際は留意しましょう。
本記事で解説したPBRのような指標を活用して企業を見極めるためには、ほかの指標と合わせた総合的な判断や、市場環境の影響の考慮など、専門的な知識や経験が必要となります。
プロレド・パートナーズでは50費目以上に専門のコンサルタントを配置し、様々な業界・業種の企業様のご相談にお応えしてきました。本記事でご紹介した経営戦略の策定・実行をはじめ、業務見直しやコスト削減を通じ、様々な業界・業種の企業様をご支援してきました。ご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。