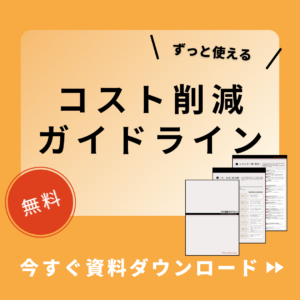貸借対照表(B/S)は、企業の財政状態を把握するための重要な財務諸表です。貸借対照表上に示される、「資産」「負債」「純資産」の構成を理解し、各指標を用いて企業の状態を分析することで、企業の経営状態や財務の健全性を評価することができます。
この記事では、貸借対照表(B/S)とは何か、貸借対照表の見方、貸借対照表を用いた企業の分析方法について解説します。
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。
貸借対照表(B/S)とは

貸借対照表(Balance Sheet、略してB/S)とは、企業の一定時点における財政状態を示す重要な書類です。一般的に会計においては、損益計算書(P/L)と並ぶ最重要な財務諸表とされています。
貸借対照表上には、特定の時点(例えば決算日時点)の、企業の「資産」「負債」「純資産」が一覧で示されるため、それぞれの構成を確認できるほか、企業の状況の分析に活かすことができます。
貸借対照表は、左側(借方)に資産、右側(貸方)に負債と純資産が記載される様式になっており、両者の合計は常に一致します。これを「貸借が一致する」といいます。
常に貸借が一致する性質から、「貸借対照表」「Balance Sheet(バランスシート)」という名称がつけられています。
貸借対照表は、企業が作成し自社の状況を把握するほか、外部に財務状況を示す手段になっています。
例えば、投資家がその企業に投資するかどうか決める際に参照するほか、金融機関が融資などを行う判断材料にします。
貸借対照表の見方

貸借対照表の見方について、さらに詳しく解説していきます。
次の部門別・項目別に説明していきます。
- 資産の部
- 負債の部
- 純資産の部
資産の部
資産の部は、貸借対照表の左側(借方)全体にあたるもので、企業が保有する資産を示します。これには企業が保有する経済的価値のある財産すべてが該当します。
次に説明する、流動資産、固定資産、繰延資産など、すべての資産を包括する項目です。
流動資産
流動資産とは、企業の保有する資産のうち、通常の営業活動から生じる資産や、1年以内という短期間で現金化可能な資産を指します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 現金及び預金
- 売掛金
- 受取手形
- 棚卸資産
- 有価証券(短期)
企業の流動資産は、すぐに使用可能な資産か、1年以内に現金化可能な資産であるため、企業の短期的な支払い能力を示す指標と判断されます。
そのため、資産の部のうち、流動資産の割合が少ない場合、支払い能力に不安がある企業とみなされることもあります。
固定資産
固定資産は、企業が保有する資産のうち、1年以上の長期にわたって使用される資産を指します。企業が事業を継続するため、また長期的に成長するための投資的な意味合いを持つものです。
固定資産はさらに、「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の3つに分かれます。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 有形固定資産:建物、土地、機械設備など
- 無形固定資産:ソフトウェア、特許権、商標権、のれんなど
- 投資その他の資産:子会社株式、長期投資など
資産として物理的に所有する有形固定資産と比較して、無形固定資産や投資その他の資産は内容がわかりづらいことがあります。
特に、無形固定資産は、ソフトウェアなどを保有する企業の増加によって複雑化しているといわれています。今後、新リース会計基準の適用が予定されるなど法改正の影響も見込まれており、最新の法令情報に照らして処理する必要があります。
繰延資産
繰延資産はほかの資産項目と性質が大きく異なります。繰延資産として処理されるものは、すでに行われた支出のうち、その効果が将来にわたると認められる費用であり、この長期的な効果を会計上形式的に資産として処理するものです。
これらは実際には現金化して使用できる資産ではないため、注意が必要です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 広告費のうち効果が1年以上続くと考えられるもの
- 創立費
- 開業費
- 社債発行費
繰延資産の取り扱いは会計上と税務上で異なる場合があります。また、関係法令の改正によって処理の基準が変更になることもあるため注意が必要です。
負債の部
負債の部は、貸借対照表の右側(貸方)に記載される企業の債務を示します。これには企業が金融機関から借りているお金や、将来支払わなければならない買掛金などが含まれます。
負債の部は資産の部と同様に、負債の性質によって、流動負債、固定負債といった項目に分類されます。
流動負債
流動負債とは、企業がもつ負債のうち、1年以内に支払い期限・返済期限を迎える債務を指します。通常の企業活動で頻繁に発生するものが多いです。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 買掛金
- 支払手形
- 短期借入金
- 未払金
- 未払費用
- 未払法人税等
固定負債
固定負債は、企業がもつ負債のうち、支払い期限や返済期限が1年以上先である長期的な債務を指します。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 長期借入金
- 長期未払金
- 社債
- 繰延税金負債
通常、固定負債に該当するものには、大規模な設備投資や事業拡大を目的のための長期的借入金や、高額な機械を分割で購入、もしくはリース契約した場合の未払金が含まれます。
ただし、固定負債に含まれる「繰延税金負債」はこれらと性質が異なる特殊な項目です。
これは、資産の部で説明した「繰延資産」と似ており、将来的に支払うことになる税金の見積もり額を、会計上形式的に負債として計上するものです。
純資産の部
純資産の部は、企業が保有する資産から負債を差し引いた残りの部分であり、貸借対照表では、負債と並んで右側(貸方)に記載されます。これは、企業に返済義務などがなく自由に使える資産を指します。
純資産の部の内訳は以下です。
- 株主資本:株主からの出資と企業が得た利益の蓄積の合計から、自己株式を差し引いたもの
・資本金:株主からの出資金
・資本剰余金:株主からの出資金のうち資本金として計上されなかった部分
・利益剰余金:企業が過去に得た利益のうち配当として支払われずに内部に留保された部分
・自己株式:企業が自社の株式を取得した際に計上される項目、株主資本から控除(貸借対照表上ではマイナスの金額で記載する)
- 評価・換算差額等:資産を時価評価した際の含み益・含み損
- 新株予約権:将来の株式発行に関連する権利
- 非支配株主持分:親会社が子会社に対して持つ持分のうち、親会社以外の株主が保有する部分
純資産は「自己資本」と混同されることがありますが、これらは厳密には定義が異なります。自己資本とは、純資産から新株予約権と非支配株主持分を除いたものです。企業によっては、純資産の額と自己資本の額が変わらないというケースもあるため、純資産と自己資本が同様に扱われることもあります。
貸借対照表の分析方法

貸借対照表を詳細に分析することで、企業の財務状態や経営の健全性を判断することができます。資産全体の数字だけを見ても実態がわからないというケースも多いです。
例えば、総資産の数字が大きいが、棚卸資産や売掛金が極端に多い場合、それらがスムーズに現金化されていれば問題ありませんが、そうでなければ、資金繰りに難航している可能性があります。数字上は資産が多く見えても、実際にはキャッシュ不足に陥っている企業は少なくありません。
このような企業の実態を見極めるためにも、貸借対照表を読むことから一歩踏み込んだ分析を実施しましょう。
貸借対照表を分析する際の主な指標について解説します。
- 自己資本比率
- 自己資本利益率
- 流動比率・当座比率
- 固定比率
- 負債比率
自己資本比率
自己資本比率とは、企業の総資本に対する自己資本の割合を示すものです。
自己資本とは、企業が有する資金のうち返済が不要なものであり、一般的にこの比率が高いほど企業の財務的な安定性が高いとされます。
計算式は以下の通りです。
自己資本比率=自己資本÷総資本×100
自己資本利益率
自己資本利益率(ROE)とは、自己資本に対する当期純利益の割合を示すものです。この指標は、自己資本に対してどれだけの利益を上げているかを示すため、企業の収益性を測ることができます。
計算式は以下の通りです。
自己資本利益率(ROE)=当期純利益÷自己資本×100
自己資本利益率(ROE)について詳しくは、以下コラムも参考にしてください。
ROEとは?ROA・ROIとの違いや数値からわかることを詳しく解説
流動比率・当座比率
流動比率は、流動資産と流動負債の割合を示す指標で、短期的な支払い能力を評価するものです。一般的に、流動比率が高いほど、短期的な支払い能力が高いとされます。
計算式は以下の通りです。
流動比率=流動資産÷流動負債×100
これに対して、当座比率は、流動資産から棚卸資産などの実際の流動性が低いものを除いた資産(当座資産)と流動負債の割合を示します。流動比率よりも厳密に短期的な支払い能力を測ることができます。
計算式は以下の通りです。
流動比率=当座資産÷流動負債×100
固定比率
固定比率は、固定資産が自己資本に対してどの程度の割合を占めているかを示すものです。
これは、企業が長期的な投資を自己資本によってどの程度まかなっているかを表すもので、この比率が高いと、借入金などの他人資本に依存していることを示します。
計算式は以下の通りです。
固定比率=固定資産÷自己資本×100
負債比率
負債比率は、企業の自己資本に対する負債の割合を示すものです。この比率が高いと、企業が借入金などの負債に依存していることを示し、財務リスクが高いと判断される可能性があります。
ただし、企業のフェーズや成長戦略によって資金調達の状況などは異なるため、一概に高いから危険という判断もできません。
計算式は以下の通りです。
負債比率=負債÷自己資本×100
まとめ
貸借対照表は、企業の財政状態を把握するための重要な財務諸表であり、経営や資金繰り、財務安全性を確保するうえでも不可欠な書類です。
貸借対照表の作成は多くの企業に義務付けられていますが、作成して終わりにするのではなく、各指標をもとに自社の状況を分析することで、より効果的に活用できるといえます。
貸借対照表をはじめとした財務諸表の分析能力は、経営だけでなく、事業運営や企業の見極めなど、ビジネスの広い場で活かされるため、読み方や分析方法を理解しておくことはビジネスパーソンにとって大きな武器にもなるでしょう。
プロレド・パートナーズでは50費目以上に専門のコンサルタントを配置し、様々な業界・業種の企業様のご相談にお応えしてきました。本記事でご紹介した財務諸表の分析をはじめ、企業の課題発見や業務見直し、コスト削減を通じ、様々な業界・業種の企業様をご支援してきました。ご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。